きっずページ
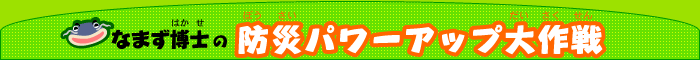 |
 |
 |
 |
雨(あめ)が降(ふ)り続(つづ)いた場合(ばあい)、土砂災害(どしゃさいがい)に要注意(ようちゅうい)!! |
|
雨(あめ)が降(ふ)り続(つづ)いたときは、地盤(じばん)がゆるんだりして土砂災害(どしゃさいがい)の発生(はっせい)する可能性(かのうせい)が高(たか)くなります。
土砂災害(どしゃさいがい)には主(おも)に、がけ崩(くず)れ災害(さいがい)、地(じ)すべり災害(さいがい)、土石流災害(どせきりゅうさいがい)があります。 |
 |
がけ崩(くず)れってなに? |
|
豪雨(ごうう)、または地震(じしん)により地盤(じばん)がゆるみ、突然崩(とつぜんくず)れ落(お)ちる現象(げんしょう)を「がけ崩(くず)れ」と言(い)います。
崩(くず)れた土砂(どしゃ)は斜面(しゃめん)の高(たか)さの2~3倍(ばい)にあたる距離(きょり)まで届(とど)くこともあります。
がけ崩(くず)れの危険(きけん)のある場所(ばしょ)は、全国(ぜんこく)で86,651箇所(かしょ)(平成(へいせい)9年調(ねんしら)べ)と、他(ほか)の土砂災害危険箇所(どしゃさいがいきけんかしょ)の数(かず)に比(くら)べて多(おお)いのが特徴(とくちょう)です。 |
|
|
|
|
|
|
| がけ崩(くず)れの前兆現象(ぜんちょうげんしょう) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
地(じ)すべりってなに? |
|
地(じ)すべりとは、緩(ゆる)やかな斜面(しゃめん)の場所(ばしょ)で、粘土(ねんど)のような滑(すべ)りやすい地層(ちそう)に雨水(あまみず)などがしみ込(こ)み、その影響(えいきょう)で地面(じめん)が動(うご)き出(だ)す現象(げんしょう)です。
広(ひろ)い範囲(はんい)にわたって起(お)こるのが特徴(とくちょう)で、家(いえ)や田畑(たはた)、道路(どうろ)などの交通網(こうつうもう)などが一度(いちど)に被害(ひがい)を受(う)けてしまいます。
地(じ)すべりは、1日(にち)に数(すう)ミリ程度(ていど)と目(め)に見(み)えないほどの動(うご)き方(かた)ですが、突然(とつぜん)ズルズルと数(すう)メートルも動(うご)くことがあります。
また、地(じ)すべりによってせき止(と)められた川(かわ)の水(みず)がいっきに流(なが)れだすと、下流(かりゅう)に大災害(だいさいがい)をもたらすこともあります。 |
 |
土石流(どせきりゅう)ってなに? |
|
谷(たに)や山(やま)の斜面(しゃめん)からくずれた土(つち)や石(いし)などが、梅雨(つゆ)の長雨(ながあめ)や台風(たいふう)の大雨(おおあめ)などによる水(みず)と一緒(いっしょ)になって、いっきに流(なが)れ出(で)てくる現象(げんしょう)が土石流(どせきりゅう)です。
「土石流災害(どせきりゅうさいがい)」は、流(なが)れの急(きゅう)な川(かわ)があるところや扇状地(せんじょうち)で起(お)こることが多(おお)く、速(はや)いスピードと強(つよ)い力(ちから)で被害(ひがい)をもたらします。 |
|
|
|
|
|
|
| 土石流(どせきりゅう)の前兆現象(ぜんちょうげんしょう) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
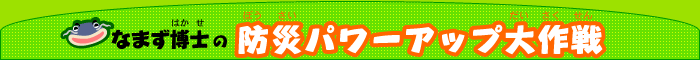 |
 |
 |
 |
雨(あめ)が降(ふ)り続(つづ)いた場合(ばあい)、土砂災害(どしゃさいがい)に要注意(ようちゅうい)!!
|
|
|
雨(あめ)が降(ふ)り続(つづ)いたときは、地盤(じばん)がゆるんだりして土砂災害(どしゃさいがい)の発生(はっせい)する可能性(かのうせい)が高(たか)くなります。
土砂災害(どしゃさいがい)には主(おも)に、がけ崩(くず)れ災害(さいがい)、地(じ)すべり災害(さいがい)、土石流災害(どせきりゅうさいがい)があります。
|
 |
がけ崩(くず)れってなに?
|
|
|
豪雨(ごうう)、または地震(じしん)により地盤(じばん)がゆるみ、突然崩(とつぜんくず)れ落(お)ちる現象(げんしょう)を「がけ崩(くず)れ」と言(い)います。
崩(くず)れた土砂(どしゃ)は斜面(しゃめん)の高(たか)さの2~3倍(ばい)にあたる距離(きょり)まで届(とど)くこともあります。
がけ崩(くず)れの危険(きけん)のある場所(ばしょ)は、全国(ぜんこく)で86,651箇所(かしょ)(平成(へいせい)9年調(ねんしら)べ)と、他(ほか)の土砂災害危険箇所(どしゃさいがいきけんかしょ)の数(かず)に比(くら)べて多(おお)いのが特徴(とくちょう)です。
|
|
|
|
|
|
|
| がけ崩(くず)れの前兆現象(ぜんちょうげんしょう) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
地(じ)すべりってなに? |
|
地(じ)すべりとは、緩(ゆる)やかな斜面(しゃめん)の場所(ばしょ)で、粘土(ねんど)のような滑(すべ)りやすい地層(ちそう)に雨水(あまみず)などがしみ込(こ)み、その影響(えいきょう)で地面(じめん)が動(うご)き出(だ)す現象(げんしょう)です。
広(ひろ)い範囲(はんい)にわたって起(お)こるのが特徴(とくちょう)で、家(いえ)や田畑(たはた)、道路(どうろ)などの交通網(こうつうもう)などが一度(いちど)に被害(ひがい)を受(う)けてしまいます。
地(じ)すべりは、1日(にち)に数(すう)ミリ程度(ていど)と目(め)に見(み)えないほどの動(うご)き方(かた)ですが、突然(とつぜん)ズルズルと数(すう)メートルも動(うご)くことがあります。
また、地(じ)すべりによってせき止(と)められた川(かわ)の水(みず)がいっきに流(なが)れだすと、下流(かりゅう)に大災害(だいさいがい)をもたらすこともあります。 |
 |
土石流(どせきりゅう)ってなに?
|
|
|
谷(たに)や山(やま)の斜面(しゃめん)からくずれた土(つち)や石(いし)などが、梅雨(つゆ)の長雨(ながあめ)や台風(たいふう)の大雨(おおあめ)などによる水(みず)と一緒(いっしょ)になって、いっきに流(なが)れ出(で)てくる現象(げんしょう)が土石流(どせきりゅう)です。
「土石流災害(どせきりゅうさいがい)」は、流(なが)れの急(きゅう)な川(かわ)があるところや扇状地(せんじょうち)で起(お)こることが多(おお)く、速(はや)いスピードと強(つよ)い力(ちから)で被害(ひがい)をもたらします。
|
|
|
|
|
|
|
| 土石流(どせきりゅう)の前兆現象(ぜんちょうげんしょう) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
三重県 防災対策部